第1章:成功への必須要素

さて、本格的にVDOT理論を紹介する前にまず私のランニング哲学について紹介しておこう。

そんなのより速く走れるようになる理論をさっさと教えろお。

理論を教えるのは簡単だが、まずはそこに至る背景をしっかりと理解することが重要なんだ。基礎がしっかりしていないとその上にいくら積み上げても崩れてしまうかもしれないだろう?
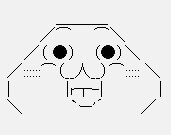
わかったお、とりあえず第1章は「成功への必須要素」というタイトルだけどどういうことだお?

私はこれまでたくさんのランナーを指導してきたが、全員が等しく成功できたわけではなかった。だが、成功するものたちにはある共通点があった。それが「先天的な能力」、「意欲」、「チャンス」、「指針」の4つでこの順に重要だ。

「先天的な能力」・・・つまり才能がないと大成できないということを最初に主張されるとは夢も希望もないですね

残念ながらトップアスリートたちは皆等しく努力しているし、先天的な能力に関してはいくらコーチが優秀で本人が努力しようとどうしようもない。

スラムダンクで陵南高校監督の田岡茂一が魚住に言った「お前をでかくすることはできない、たとえオレがどんな名コーチでもな。立派な才能だ。」はまさに真理ですね。

バスケの場合は身長が重要なファクターなのは疑いようがないが、優れたランナーの条件は外見からは分かりづらい。VO2maxが高い、ランニングエコノミーが高いなどは運動生理学テストを受けないとわからないからね。

2つ目に挙げられているのは「意欲」ですね

やる夫も意欲だけはあるお

どんなに優れた才能を持っていても強い意欲がなければ大成できないだろう。稀に練習嫌いで才能だけでやっているスポーツ選手もいるが、そのような選手が栄光を掴めることはないし、あったとしても一時的だろう。

佐藤清治選手などは才能がありながらも意欲が続かなかった代表例でしょうね。

3つ目は「チャンス」かお。運任せとかこればかりはどうしようもないお。

環境に恵まれているかどうかも重要な要素だ。だがランニングはどんな環境でもできるのが魅力の一つでもあるし、例えどんな状況でも実りのある練習をすることは可能だ。

最後は「指針」ですね。これは育成方針ということでしょうか。

その通り、コーチから適切な指導を受けられるかどうかも成功の要素だ。だが指導者の評価は難しい。指導者は選手の成績によってのみ評価されるからだ。私が考える良い指導者とは、トレーニングを通して選手をより良いランナーに、そして人間に育てることのできる存在である。
ダニエルズのランニング基本原則

上で挙げた4つの成功の必須要素とは別に、次の10個の基本原則を挙げておく。同じ指導をしても選手によって反応は様々に異なるため、個々のトレーニング状況を評価し向上させるために、この基本原則が役に立つ。
- 選手はそれぞれ固有の能力を持っている
- ポシティブなことに目を向ける
- 良い時もあれば悪い時もある
- 予想外のことに備えトレーニングには柔軟性を持たせる
- 中期目標を設定する
- トレーニングにやりがいを
- 良質の食事と睡眠をとる
- 病気にかかっている時、怪我をしている時はトレーニングをしない
- 慢性的に身体の不調があったら医師の診察を受ける
- うまく走れた、いいレースができた、という時、それは決してまぐれではない

多すぎるお、1つずつ解説してお。

まず「1.選手はそれぞれ固有の能力を持っている」ですが、これはスピードタイプかスタミナタイプかってことですかね?

その通り、同じ練習をしていてもその練習に対する反応は異なる。筋繊維の割合がすでに先天的なものだからね。

「2.ポシティブなことに目を向ける」とは?

毎回100%練習をこなせる選手はいない。良いときもあれば悪いときもある。悪い時は過度に悲観的にならず、良かったことに目を向けよう。

「3.良い時もあれば悪い時もある」これは2.と似ていますが?

悪いときは無理にがんばらず、途中棄権することも必要だろう。

「4.トレーニングに柔軟性をもたせる」って柔軟トレーニングをしろってことかお?

計画通りにいくことは少ないため、何かあってもリカバリできるような柔軟性が必要ってことですね。

「5.中期目標を設定する」ってことはやる夫がサブ3するって宣言したらその中間目標も設定しろってことかお?

いきなり大きな目標を立ててもダメで、そこに至るまでの道筋が見えないと達成できないだろう。そのためにマイルストーンを設定することは重要だ。

サブ3をするためにIペース3’40″/kmで走れるようにしたいから、まずは3’45″/kmをクリアする、という感じですかね。

「6.トレーニングにやりがいを」は重要だお。単調なトレーニングは続かないお!

トレーニングを続けられるのは効果を実感できるからだ。何も変わらないのに辛いトレーニングを続けることはできない。トレーニングの目的を理解すれば、自分が成長しつつあることがわかるようになるはずだ。
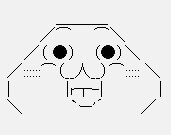
「7.良質の食事と睡眠を取る」はよく分かるお。やる夫もよく食べてよく寝る子だお!

休養と栄養はトレーニングの一部である。トレーニングと切り離して考えるものではない。

「8.病気にかかっているとき、ケガをしているときはトレーニングをしない」か。多くのランナーは耳が痛いと思いますが。

2~3日休めば回復するようなケガでも無理したらさらに休むことになるだろう。

耳が痛いです・・・

「9.慢性的に体の不調があったら医師の診察を受ける」か。やる夫もすぐ医者にいくようにするお!

慢性的な不調が長く続くようなら治療が必要な事態が多い。

ランナーの場合、貧血で慢性的に不調になるケースが多い気がします。

「10.うまく走れた、いいレースができた、というとき、それは決してまぐれではない」、これは深いですね。

長距離走にマグレはない、スタートラインに立った時点で結果はほぼ出ているんだ。
第1章のまとめ

まだ全然VDOTの話が出てこないお。今回はランニング哲学的な話ばっかりだったお。

VDOTが出てくるのは5章からだ。その前に背景となるランニング哲学や運動生理学の知識を積み上げていく必要がある。

今回は成功への必須要素4つと、ランニングの基本原則10個について語っていただきました。

テストに出るから復習しておくように。

何のテストだお・・・
続く・・・




コメント